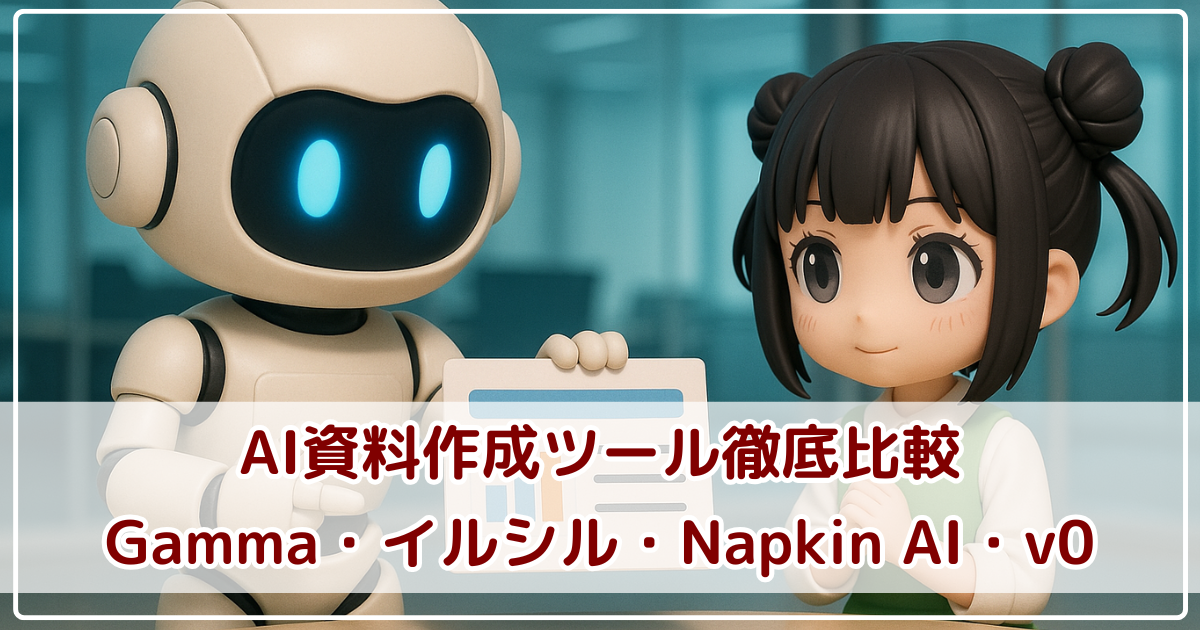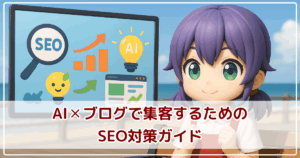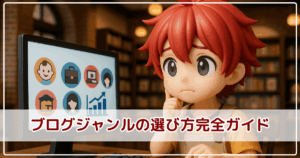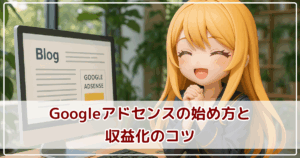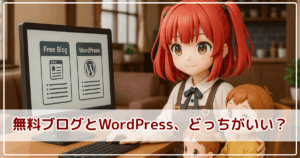資料づくりにもAIが活躍する時代になりました。プレゼン用のスライド、SNS映えする図解、LPの自動生成まで、目的に応じたツールが続々登場しています。
本記事では、注目のAI資料作成ツール「Gamma(ガンマ)」、「イルシル」、「Napkin AI(ナプキンエーアイ)」「v0(ブイゼロ)」の特徴を比較。
それぞれの強みや活用シーンをやさしく解説しながら、ツール選びに役立つヒントをお届けします。
AI資料作成ツールとは?どんな場面で使えるの?
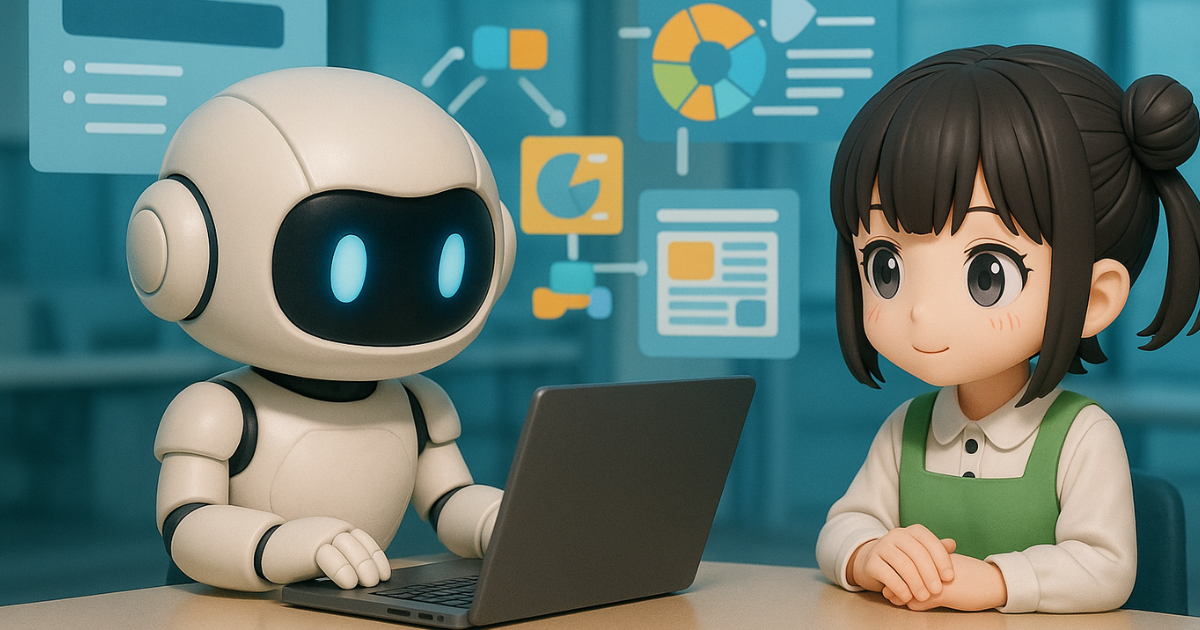
最近は、ただ文章を書くAIだけでなく、スライドや図解、Webページ(LP)まで作れてしまうツールが増えてきました。
ここでは、どんな作業にAI資料作成ツールが使えるのか、実際の活用シーンを交えながらご紹介していきますね。
スライド・図解・LPまでAIが作れる時代に

えっ、資料までAIが作ってくれるの?
そんな驚きの声が聞こえてきそうですが、実は今、多くの作業がAIに任せられるようになっています。
資料作成といえば、プレゼン資料・図解入りの解説・キャンペーン用のLP(ランディングページ)など、手間と時間がかかる作業の代表格です。
でも最近のAIツールは、「スライドの構成から見栄えの良いデザインまで一括で作れる」ものが主流になってきています。
たとえば、長い説明文を入力すると、そのままスライド化してくれるGammaや、図解化してくれるNapkin AIなどがその例です。
しかも、テンプレートやデザインの提案も自動で行ってくれるので、資料づくりが苦手な方でも安心して取り組めるようになりました。
アイデアや内容はあるのに形にするのが大変…そんな方にとって、AI資料作成ツールはまさに頼れるパートナーです。
手間を減らして見栄えよく!メリットとは



正直、見た目を整えるのが一番たいへんなんです。
資料を作るとき、内容を考えるだけでも大変なのに、レイアウトやデザインまで整えるのってなかなか時間がかかりますよね。
でもAI資料作成ツールを使えば、デザインや構成を自動で整えてくれるので、自分で「どこに何を置くか?」と悩まなくていいんです。
たとえば、Napkin AIならテキストを打ち込むだけで図解化してくれるし、Gammaなら長文をスライドに分けて配置してくれます。
人がやると時間がかかる“見栄え”の部分をAIが先に整えてくれるので、内容に集中できるのも大きなメリットですね。
しかも、テンプレートや配色も自動提案されるので「デザインセンスが不安…」という方にも安心です。
見やすく、わかりやすく、しかも短時間で資料ができる。これだけで作業効率がぐんと変わってきますよ。
ツール選びは目的に合わせるのがコツ



たくさんあって、結局どれがいいのか分からなくなっちゃいます。
AI資料作成ツールもそれぞれに特徴があるので、“何を作りたいのか”によって選び方が変わってきます。
たとえば、プレゼン資料や長文ベースの説明ならGammaが向いています。
反対に、SNSでシェアしたくなるような図解を作るなら、Napkin AIのようなビジュアル重視のツールが活躍します。
また、「LP(ランディングページ)を丸ごと作りたい」なら、V0のようにページ構成からコピー作成まで対応したツールが最適です。
操作のシンプルさや、日本語対応を重視するならイルシルのような日本製ツールを選ぶのも一つの方法ですね。
なんとなくで選ぶと「自分の用途には向いてなかった…」と感じやすいので、まずは「何に使うか?」を明確にしてから選ぶのが失敗しないコツです。
慣れてくれば、複数のツールを場面ごとに使い分けるのもおすすめですよ。
Gamma:スライド型資料×長文対応で万能
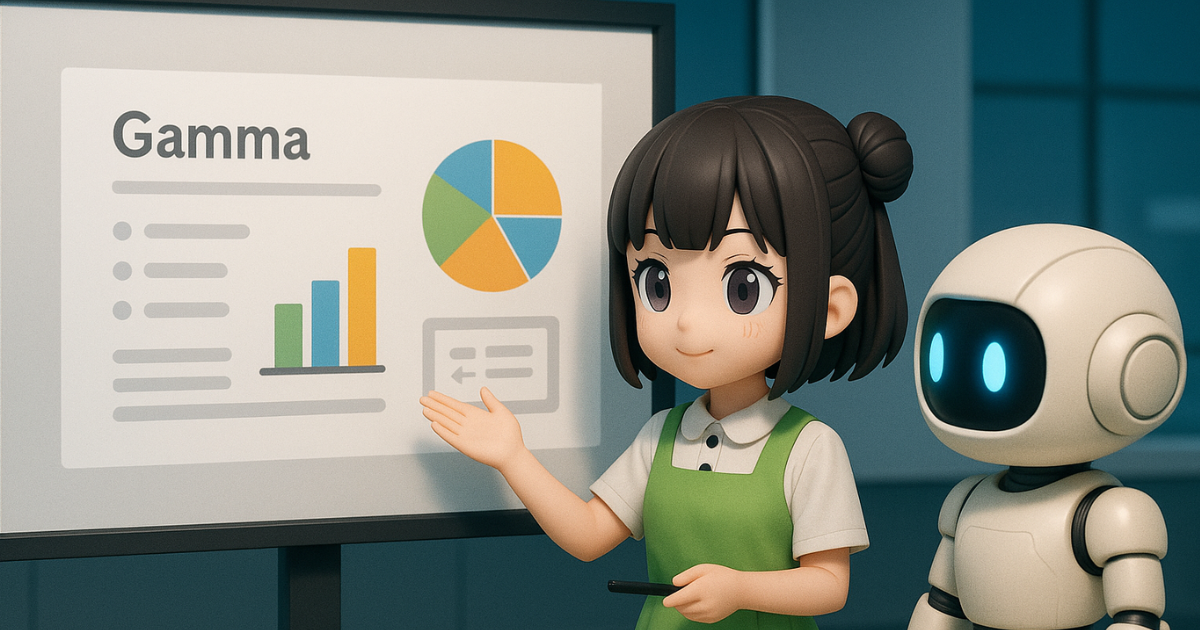
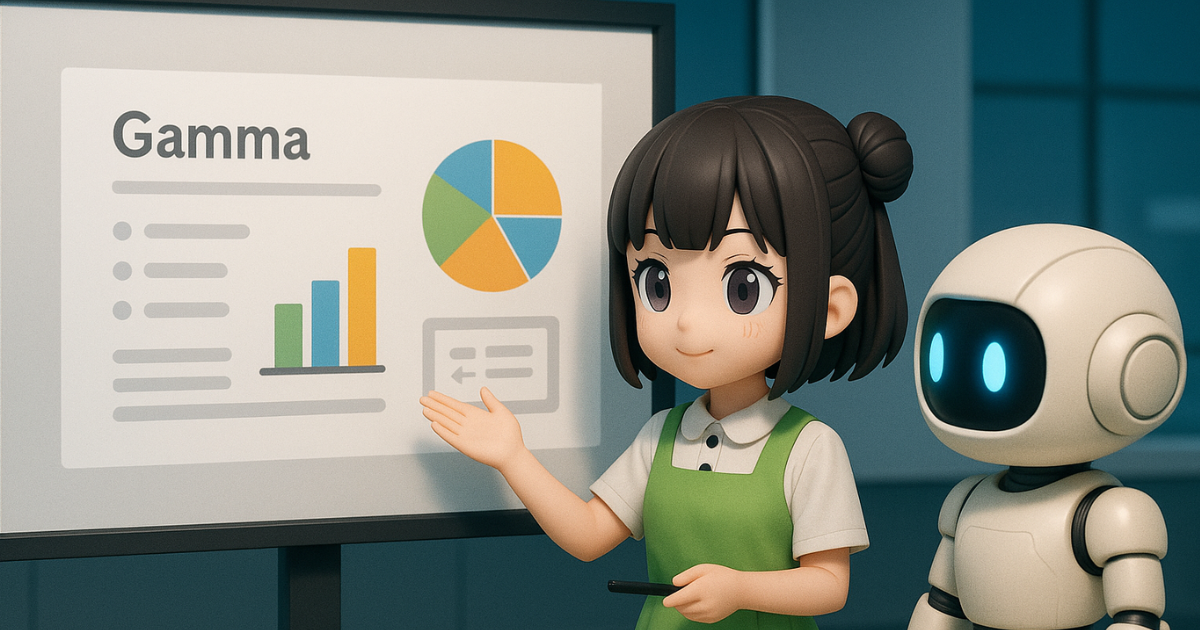
Gamma(ガンマ)は、スライド型の資料作成を得意とするAIツールです。長文プロンプトにも対応していて、プレゼンや企画書のような情報量の多い資料にも強いのが特長です。ここでは、Gammaの使いどころや活用法をくわしく見ていきましょう。
プレゼン資料に強い!構成も自動提案



スライドの流れを考えるのが苦手で…助かってます。
Gammaの魅力は、プレゼン資料に必要な構成を自動で組み立ててくれるところです。たとえば、「○○について説明したい」と入力するだけで、導入→要点→まとめという自然な流れを持ったスライド構成を提案してくれます。
しかも、各スライドに入るべき情報まで整えてくれるので、「何をどこに入れればいいか分からない…」という悩みも解消されます。
資料全体の一貫性を保ちながら、見た目もきれいに整えてくれるのがうれしいですね。
また、レイアウトのテンプレートも豊富で、ビジネスっぽい硬めの資料から、やわらかく親しみのあるスライドまで、トーンに合わせて選べます。
プレゼンの準備時間が取れないときや、構成に自信がない方には、Gammaはとても頼れる存在です。
長文プロンプトで細かい指示にも対応



ふわっとした指示でも、ちゃんと読み取ってくれるんです。
Gammaは、長めの指示文(プロンプト)にも的確に対応できるAIツールです。「ターゲットは30代女性」「この順番で説明して」など、細かい指定を盛り込んだ文章をそのまま入力するだけで、意図をくみ取ってスライドを作成してくれます。
特に便利なのが、構成・トーン・伝えたい内容まで一括で指示できる点です。たとえば、「親しみやすい口調で」「3ステップで紹介」などと伝えれば、スライドごとにそれに沿った表現でまとめてくれるんですね。
もちろん、生成された内容は後から微調整も可能なので、「まずはざっくり作って、あとで整える」という使い方にも向いています。
プレゼンや資料作成で、「ここまで言わないと伝わらないかも…」と不安になる方でも安心です。柔軟に指示をくみ取ってくれるのは、Gammaならではの強みですよ。
SNS用スライド投稿にも活用できる



投稿に“映え”を出したいとき、すごく便利です。
Gammaは、ビジネスだけでなくSNS向けのスライド型コンテンツ作成にも相性バツグンです。Instagramのカルーセル投稿や、X(旧Twitter)でのスレッド風スライド投稿など、視覚的にインパクトのある投稿がサクッと作れます。
たとえば、「○○のコツを5枚で紹介したい」「初心者向けに図解で見せたい」といった要望にも、Gammaはしっかり対応してくれます。
色やフォントも整った状態で出力されるため、デザインが苦手な人でも安心です。さらに、タイトル・本文・要点をバランスよく配置してくれるため、読み手にやさしい構成になるのも魅力。
マーケティングや発信活動に力を入れたい方は、SNS向け資料づくりにGammaを取り入れると、表現の幅がぐんと広がりますよ。
イルシル:日本語×シンプル操作で使いやすい
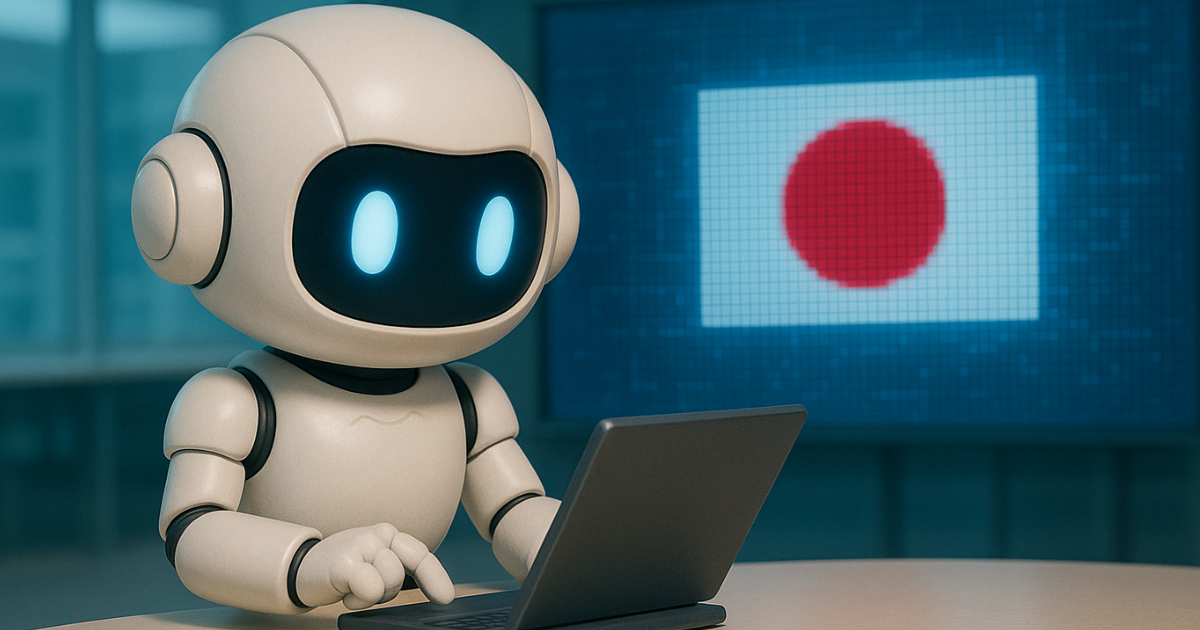
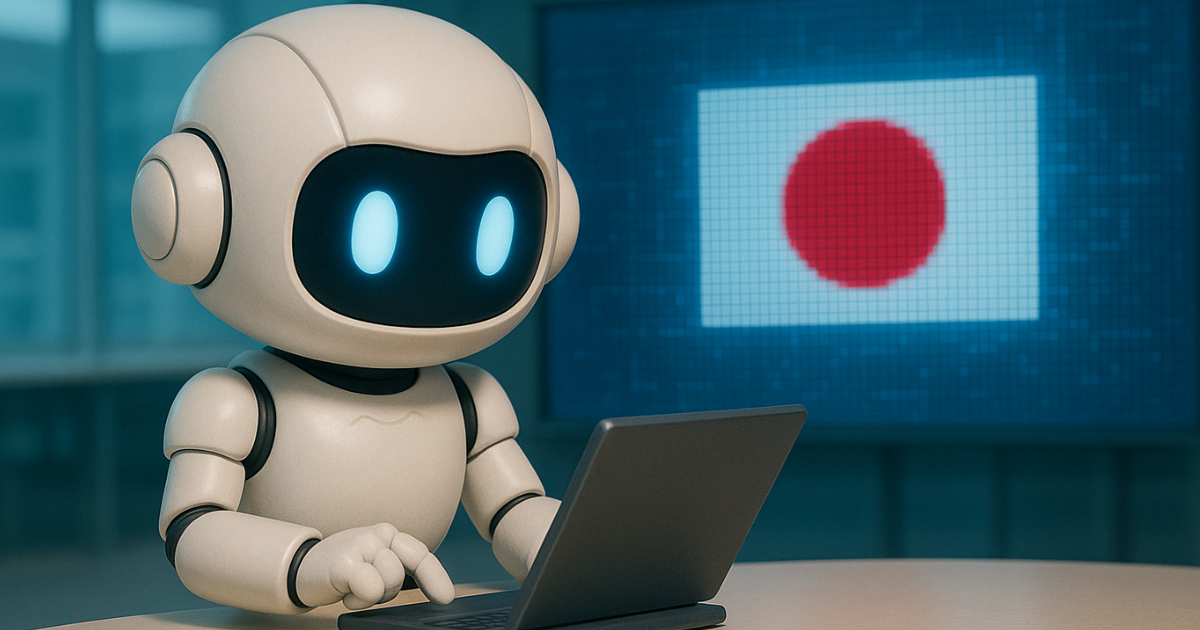
イルシルは、国産の資料作成AIツールです。直感的に使える設計と、日本語に強い出力が特長。提案資料やプレゼント資料など、かしこまりすぎず、それでいて整った印象の資料づくりにぴったりです。
ノーコードでサクッと資料化



難しい操作はゼロ。それでいて、仕上がりは整っていて感動しました。
イルシルの魅力はなんといっても「誰でも使える手軽さ」です。特別なソフトのインストールや、複雑な操作はいっさい不要。テキストを入力するだけで、AIが自動的にレイアウト・色使い・構成を整えてくれます。
特にありがたいのが、ノーコードで資料が完成するスピード感。アイデアや下書きメモを貼り付ければ、1〜2分で見映えのいい資料に変わります。
また、イルシルは日本語に最適化されているので、出力される文章も自然で読みやすいんです。「この言い回し、ちょっと変かも?」という心配が少ないのはうれしいポイントですね。
「資料づくりは苦手だけど、ちゃんと整ったものを作りたい」という方に、イルシルはちょうどいい相棒になってくれますよ。
日本語表現が自然!提案資料にも◎



自分で書いたみたいな自然さに、思わずびっくりしました。
イルシルは日本語に特化したAIなので、出力される文章の違和感がとても少ないです。たとえば、よくある翻訳っぽい不自然な表現や、硬すぎる言い回しが目立ちません。
提案資料をつくるときって、「わかりやすくて、でもビジネス的な表現もほしい」という場面が多いですよね。イルシルは、そのちょうどいい“間”を保ってくれるのが強みなんです。
たとえば、「〜してみませんか?」のような柔らかい語りかけも、「〜をご提案いたします」といったビジネス表現も、状況に合わせて自然に使い分けてくれます。
読み手に寄り添う文章を出してくれるので、商談資料や提案スライドにも安心して使えます。シンプルに、でも伝わる。そんな資料を目指す方にぴったりです。
無料プレゼント資料に最適な仕上がり



“おしゃれだけど読める”このバランスがちょうどいいんです。
イルシルは、無料プレゼント用の資料作成にもとても向いています。たとえば、LINE登録やメルマガ登録後に渡す“お役立ちPDF”など、サクッと読めて、見映えもする資料がすぐ作れます。
魅力的なのは、色使いやデザインが整っているのに、主張しすぎないところ。SNS映えを狙った“派手さ”ではなく、あくまで内容を引き立てる“上品な仕上がり”になるのが特徴です。
また、ページ数が多くなってもレイアウトのブレが少なく、読みやすさが保たれるのも安心ポイントです。テンプレート選びで迷った場合も、AIが構成を提案してくれるので迷いません。
情報をしっかり伝えたいけど、デザインも妥協したくない。そんな方にこそ、イルシルはおすすめです。
Napkin AI:SNS映え図解が強み


Napkin AI(ナプキンエーアイ)は「わかりやすい×目をひく」を両立できる図解特化型ツール。テキストを入力するだけで、視覚的に伝わる図やチャートを作成してくれるので、SNSや講座資料などにぴったりです。
テキスト→図解を自動変換



まさか文章が、ここまでキレイな図になるなんて驚きました。
Napkin AIの最大の魅力は、テキストを入力するだけで図解に変換してくれる手軽さです。たとえば「○○の手順」「○○の比較ポイント」など、リスト形式の文章を入れるだけで、自動的に整ったチャートや図として出力してくれます。
これまでは「図を作るのが苦手」「PowerPointやCanvaが面倒」という方も多かったと思います。でもNapkin AIを使えば、デザインスキルがなくても、伝わるビジュアルが完成するんです。
操作もとてもシンプルで、難しい設定や編集も不要。特に「言葉では伝わりにくい内容を、パッと見で伝えたい」ときに大活躍してくれます。
SNS投稿やスライド資料、学習教材まで、幅広く応用できる図解AIとして注目の1本です。
カラフルで直感的、視覚に刺さる



ひと目でパッと伝わるって、やっぱり大事ですよね。
Napkin AIの出力は、色づかいやレイアウトがとても華やかで目を引くのが特長です。図解といっても堅苦しい印象はまったくなく、直感的に理解しやすいデザインが自動で仕上がります。
たとえば、比較図やプロセス図なども、単なる四角の羅列ではなく“伝わる配置と色の工夫”がされた図解になります。見る側も「なんとなく見たい気持ちになる」ビジュアルなので、SNS投稿やプレゼンにもぴったり。
もちろん、後から色やアイコンを調整することもできますが、基本は自動でかなり見栄えの良いデザインになります。視覚的な印象が大切な時代だからこそ、Napkin AIの“魅せる図解”は大きな武器になりますよ。
X(旧Twitter)やInstagramとの相性抜群



SNSでバズってる投稿、よく見ると図解が多い気がします。
Napkin AIは、SNSに投稿する前提で設計されたような図解ツールです。とくにX(旧Twitter)やInstagramでよく見かける「ひと目で理解できる投稿」に向いています。
たとえば、1テーマを簡潔にまとめた図や、3ポイントの比較をパッと整理したチャートなど。Napkin AIを使えば、そうした“流し読みでも理解できる”図をすぐ作れるんです。
図解の形も投稿向けに最適化された縦長・正方形の比率に対応していて、画像としてそのまま保存するだけでSNSにアップ可能。デザインもカラフルで目を引くので、投稿のクリック率アップも期待できます。
情報発信をしている方や、投稿の質を上げたい方には、Napkin AIがきっと頼れる味方になりますよ。
v0:LPや図解をAIで一括生成
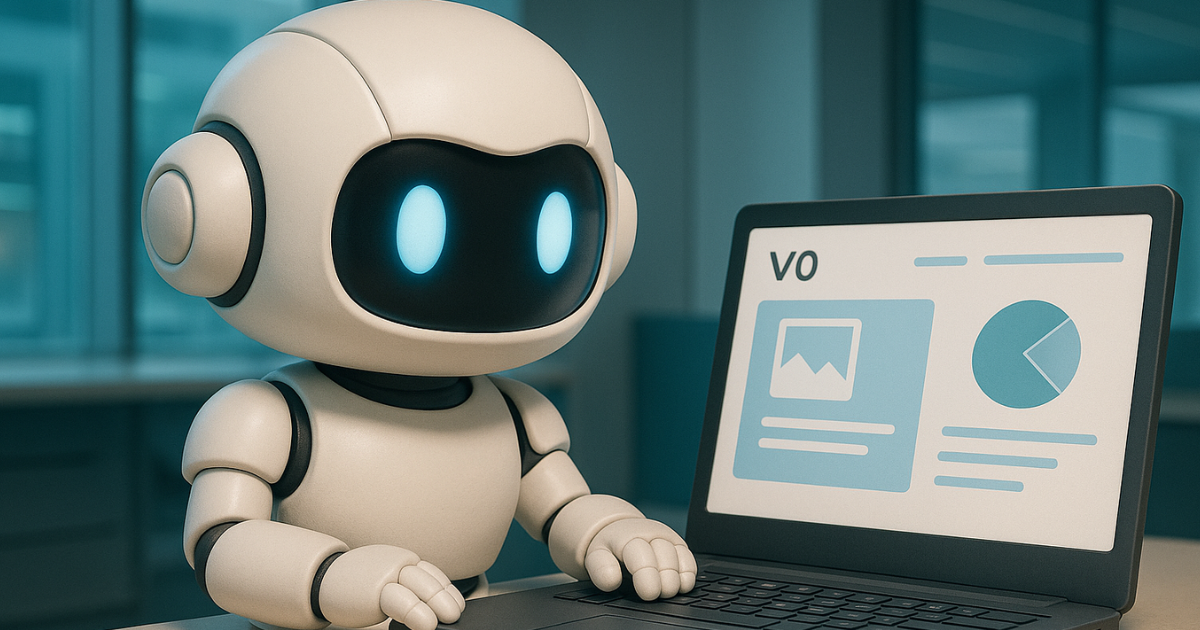
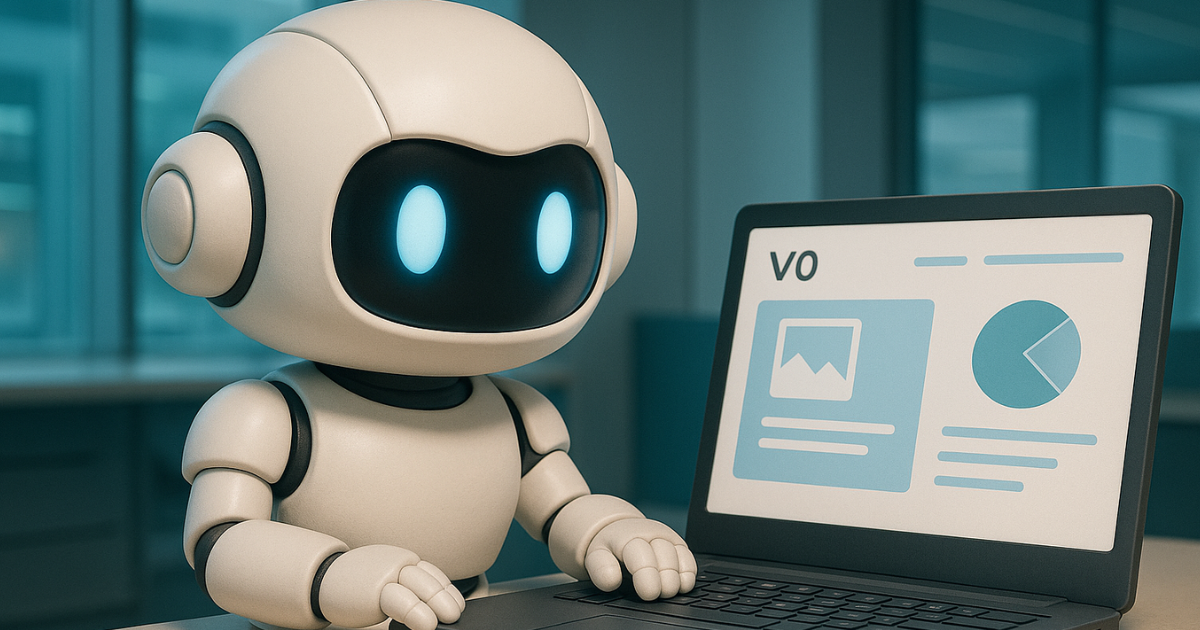
v0(ブイゼロ)は、ランディングページ(LP)制作や図解の生成をAIが自動で行ってくれる便利ツールです。文章だけでなく、構成やビジュアルまで一括で出力できるのが大きな特長です。
LP構成・デザインを一発で出力



LPって、デザインを考えるだけで時間かかっちゃいますよね。
v0がすごいのは、LPに必要な構成とデザインを、AIがセットで提案してくれることです。たとえば「○○を紹介するLPがほしい」と入力すれば、ヒーローエリア・特徴・レビュー・CTAまで、完成イメージに近い構成を丸ごと生成してくれます。
さらに、見出しやボタンの文言も含めて、具体的なコピー案まで出力されるので、「全体の流れが整ったページ」が一気にできあがります。デザインもテンプレではなく、トレンド感のある構成で提案してくれるのが嬉しいポイントです。
「時間がない」「構成が浮かばない」という方でも、v0なら最初の土台がすぐできるので、迷わず手を動かし始められますよ。ノーコードでそのまま公開することも可能なので、ページ作成のスピードが大きく変わってきます。
図解とコピーも一緒に作れて時短



文章と図を別々に作るの、けっこう大変なんですよね。
v0の便利なところは、図解と文章(コピー)を同時に自動生成してくれる点です。たとえば、サービス紹介の図を作るとき、構成だけでなく「この部分にはこのキャッチコピー」といったテキストも一緒に提案してくれるんです。
これまでは、図を作ってから文を考える、またはその逆という手間がありましたよね。でもv0なら、テーマやキーワードを入れるだけで、視覚と文章がセットになった提案が出てくるので、全体像を一気にイメージできます。
図解にぴったりな文言がすでに入っているから、編集の手間もぐっと減らせます。時間短縮だけでなく、伝わる資料をスピーディに作れるのも大きな魅力です。
フォーク機能でカスタム編集がしやすい



自動生成された内容、ちょっとだけ変えたい…ってことありますよね。
そんなときに便利なのが、v0の「フォーク機能」です。これは、既存の生成物をベースに複製し、自分好みに編集できる機能のこと。たとえば「このLPの流れはいいけど、文章だけ少し変えたい」といった時でも、一から作り直す必要はなし。
複製したあとに、見出しやカラー、図の構成などをパーツ単位で自由に調整できるので、「AIのたたき台をベースに、自分の表現に近づける」ことが簡単にできるんです。
とくに、複数パターンを比較したい時や、チームでフィードバックを回す時にも、このフォーク機能があると作業効率がかなり上がりますよ。テンプレを使いつつ、自分らしさも出したい方にはぴったりの機能です。
まとめ
AI資料作成ツールは、スライドや図解、LPまで一括でこなせる時代になりました。
Gammaは長文指示やSNS投稿にも対応し、プレゼン資料に強みがあります。イルシルは日本語に強く、初心者でも使いやすい設計が魅力です。Napkin AIは視覚的にわかりやすい図解が人気で、SNS運用に最適。v0はLPや図解を高速で出力でき、構成から編集まで一気に進められます。
目的に合わせて使い分けることで、資料づくりの時間も質も大きく変わってきますよ。